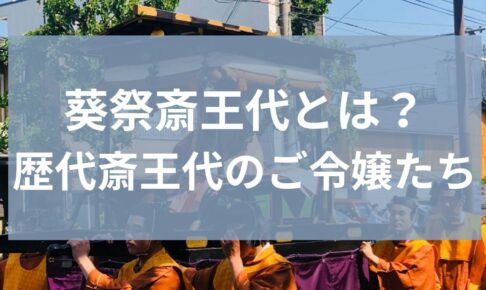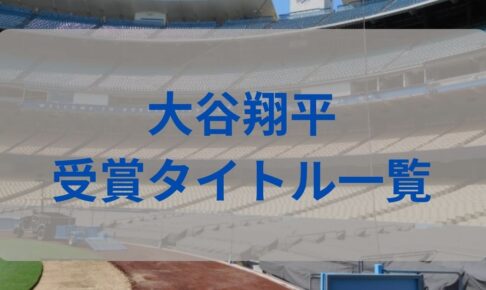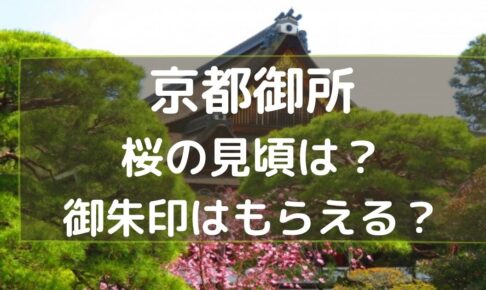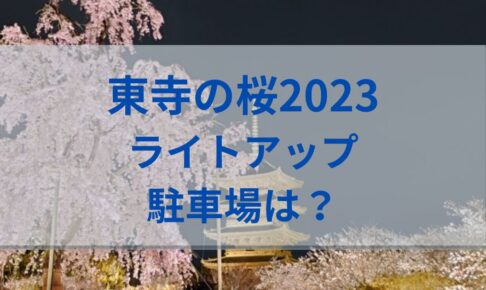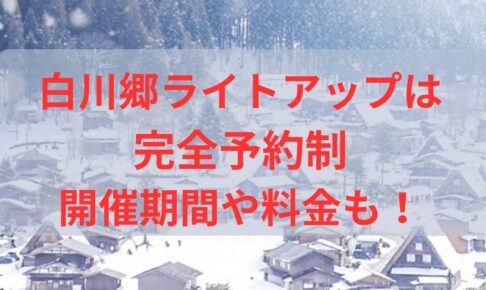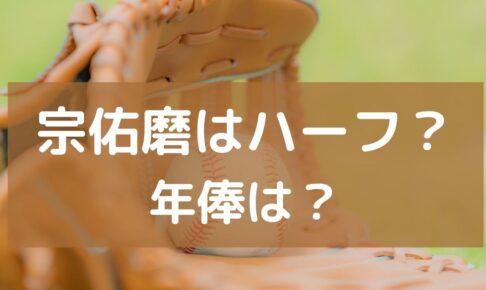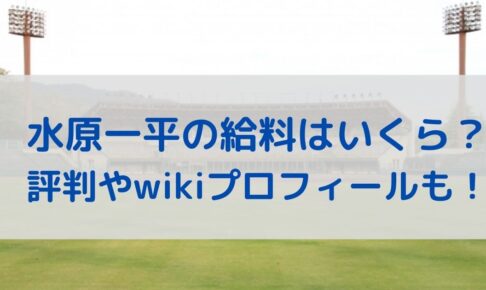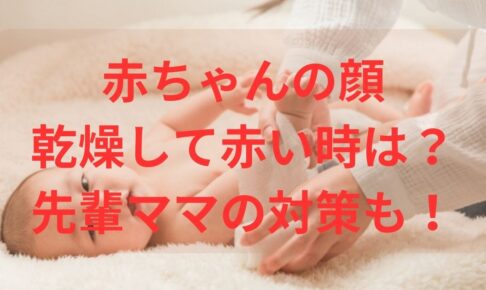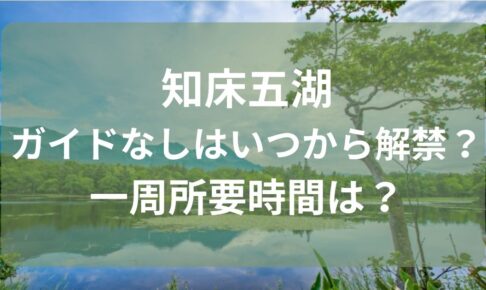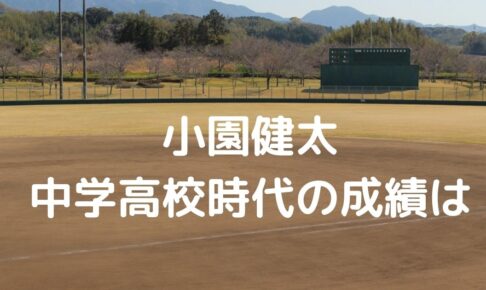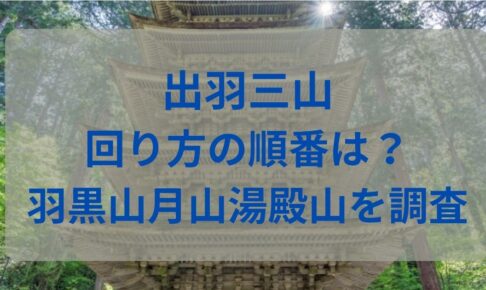京都の三大祭りのひとつ上賀茂神社と下鴨神社の例祭が「葵祭」です。行列のヒロインである斎王代の費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
斎王代に選ばれるのは名家のお嬢さんですが決め方はあるのでしょうか?歴代斎王代のお家柄が気になりますね。
今回は「葵祭の斎王代の費用はいくら?決め方は?歴代の家柄は?」と題して葵祭の斎王代を紹介します。
スポンサーリンク
葵祭とは

photo credit: Patrick Vierthaler Aoi Matsuri 2018 葵祭 via photopin (license)
葵祭は、正式には「賀茂祭」といい行列巡行の「路頭の儀」では総勢500人の行列が京都御所から下鴨神社、上賀茂神社へと都大路を平安絵巻さながらに練り歩きます。
毎年5月15日に行われていて、下鴨神社と上賀茂神社の祭礼で数少ない王朝風俗が残されています。
賀茂祭が葵祭といわれるようになったのは江戸時代元禄7年(1694年)に祭が再興されたのち御簾、牛車(御所車)、勅使等々、すべてを葵の葉で飾るようになったからといわれています。
6世紀中ごろ凶作が続いたことから賀茂神の祟りを鎮めるために馬を走らせ五穀豊穣を祈ったのが始まりだそうです。
葵祭は中断や行列の中止の時期もありましたが、王朝の伝統は忠実に守られています。
・応仁の乱(1467年~1477年)のあと元禄6年(1693年)の間約200年
・明治4年(1871年)~明治16年(1883年)の間
・昭和18年(1943年)~昭和27年(1952年)の間
・令和2年(2020年)~令和4年(2022年)の間
毎年5月15日に開催される葵祭のルートは次のとおり。
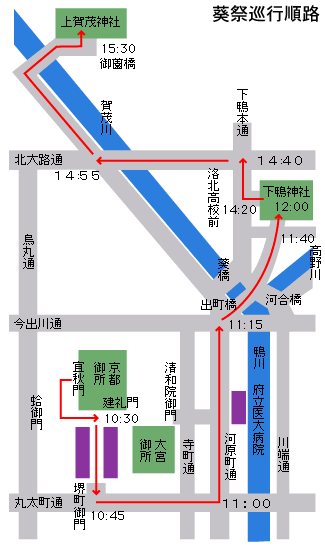
出典:e-kyoto
関連記事:葵祭のルートと有料観覧席情報!
スポンサーリンク
斎王代とは?
斎王代とは斎王の代わり、つまり代理の意味ですが元々は賀茂の社に斎王を置いていました。
伊勢神宮の斎王にならって平安時代の初期(810年)に初代斎王の有智子内親王から始まり鎌倉時代の礼子内親王まで約400年間賀茂の斎王は続きましたが、承久の乱で途絶えてしまったようです。
その後、葵祭では勅使は出ましたが斎王は復活することはなかったようです。
現在葵祭のヒロイン的な存在の斎王代ですが歴史的にはそんなに古くありません。
太平洋戦争の末期に祭は途切れていますが昭和28年(1953年)に復活しました。そして勅使の本列のみ行われました。
昭和31年(1956年)に祭を華やかなものにするため、斎王に代わる人として斎王代を立てて女人列を作ったということです。
現在の斎王代は、一般公募ではなく、葵祭行列保存会が、京都に関係しているいわば名家のお嬢さんの中から適任者を選出しています。その支度の費用は選出された側の負担となるそうですが、いったいいくらかかるのかみていきましょう。
スポンサーリンク
斎王代の費用はいくら?
昭和31年(1956年)に復活した斎王代にかかる費用はいくらくらいなのでしょうか?ちょっと気になるところですよね!
ズバリ、数千万円かかります!!
庶民にはビックリの莫大な費用が必要な斎王代!しかもこの費用は選ばれた人(家)の自腹です!!
またまたビックリです。
それではどうしてこれだけの費用がかかるのでしょうか?
斎王代は行列の時「腰輿(およよ)」という輿に乗っていますが、その時の衣装が五衣裳唐衣(いつつぎぬものからぎぬ・通称十二単)です。
なんとこの十二単は毎年新調しているのでこれだけで数百万円から一千万円はすると言われています。
そして使用後のクリーニング代も数百万円かかるそうです。
さらに行列の費用も負担しなければなりません。
その他関係者への心づけや神社への奉納料がかかるので数千万円かかるというわけです。
スポンサーリンク
斎王代の決め方は?
それでは、莫大な費用のかかる斎王代はどのようにして決めるのでしょう?ここも気になるところです!
現在、斎王代は京都在住の未婚の女性から選ばれています。一般公募ではなく、葵祭行列保存会が適任者を選びます。
まず家柄が良くなければなりません。費用負担のためにお金持ちでいいのかというと、一代で出世して財を成したお金持ちではダメなようです。つまり成金は嫌ドスエということでしょうか?
歴代の斎王代は京都の老舗などの家柄のお嬢様が選ばれています。
また斎王代に選ばれるには高学歴で、華道をはじめ茶道、日本舞踊などを特技とするような女性ともいわれています。
(裏千家のすみれ会というグループの中から選ばれることが多いとの情報もありました。)
2020年~2022年は中止されましたが、最近の歴代斎王代を見てみると、
-
令和5年(2023年)(第65代):松井 陽菜(まつい はるな)さん
京都府医師会の松井道宣会長の次女、中学2年まで京都で過ごし、イギリスに留学。ロンドン大学卒、慶応義塾大大学院修了。東京の投資会社勤務。特技は日本舞踊。 - 令和元年(2019年)(第64代): 負野 李花(おうの りか)さん
香製造販売「負野薫玉堂」の次女、同志社大学卒業。趣味は茶道。同志社高でラクロス部主将で全国大会優勝・最優秀選手賞受賞。
- 平成30年(2018年)(第63代): 坂下 志保(さかした しほ)さん
外資系投資会社社長の長女、母親は本家八ッ橋西尾専務で1988年の斎王代を務め親子2代での斎王代(6組目)、同志社大学卒業。趣味は京舞、フラワーアレンジメント。
- 平成29年(2017年)(第62代): 富田 紗代(とみた さよ)さん
不動産賃貸会社 富士興業専務の三女、同志社大学2年生 タップダンスが得意で趣味は映画鑑賞とカメラ撮影。同志社女子中・高ではソフトボール部でピッチャー。
- 平成28年(2016年)(第61代): 西村 和香(にしむら わか)さん
江戸時代前期から続く京漆器の老舗 像彦社長の長女、京都ノートルダム女子大卒業。学芸員資格を持つ。趣味は美術館巡り。
母親は1980年(第25代)斎王代を務め、親子2代での斎王代(5組目) 母親は3姉妹で妹2人も1984年(第29代)・1990年(第35代)の斎王代。
- 平成27年(2015年)(第60代): 白井 優佐(しらい ゆうさ)さん
電子部品製造会社シライ電子工業の会長の長女、日本大学卒業。趣味はクラリネット演奏 正月のおせちは全て手作りするほどの料理の腕前。
最近の歴代斎王代の経歴等は、さすがに名家の素晴らしいお嬢様という内容です!
歴代斎王代についてはこちらをご覧ください。⇒⇒葵祭の斎王代とは?歴代斎王代のご令嬢たちの名前や経歴は?
はっきりとした選考方法は不明で公募はありません。
総合すると・・・
♥ 未婚の20代の女性で行儀作法ができる
♥ 正座を長時間できる
♥ 京都にゆかりの名家
♥ 斎王代準備費用を負担できるお金持ち
斎王代の選考基準はこれらのことが最低限必要でしょう。
つまり、京都ゆかりの寺社や文化人、実業家の未婚の女性(20代)から選ばれるのが通例になっているようです。
スポンサーリンク
葵祭の余談

photo credit: Alex.Hurst Aoi Matsuri via photopin (license)
実は葵祭の行列参列者の中にはアルバイトもいるんです。
近衛使・斎王代以外の行列参列者は関係者からの推薦に加え、アルバイトも募集されています。
京都大学・同志社大学・立命館大学・京都産業大学を中心とした男子学生たちを大学を通じて募集しているようです。
過去の日当は6700円で昼食付といった条件でした! 平安装束を着られて注目を浴びるのでいい思い出になるかも!
スポンサーリンク
葵祭の斎王代の費用や決め方 まとめ
葵祭の行列巡行は5月15日午前10時半ごろ京都御苑建礼門前を出発し、下鴨神社から上賀茂神社へと練り歩きます。参加者は約511名でその中でも注目を浴びるのが斎王代です。
行列が通過するのに1時間ほどかかり混雑もしていますが、平安絵巻さながらの行列はタイムスリップしたかのようで一見の価値があるお祭りです。
今回は「葵祭の斎王代の費用いくら?決め方は?歴代の家柄は?」と題してお送りしました。
スポンサーリンク