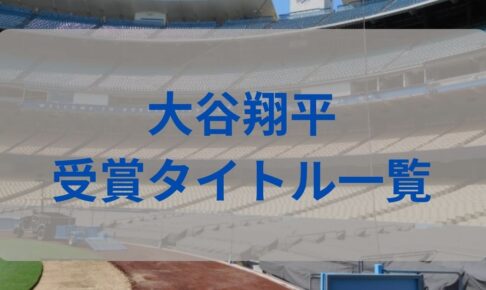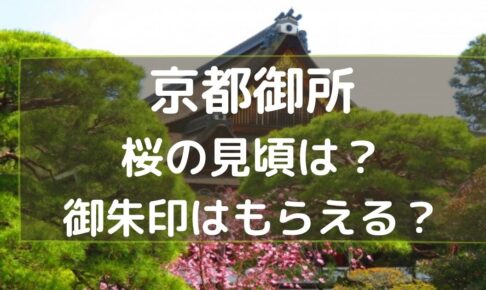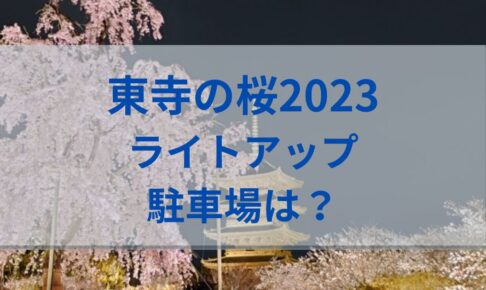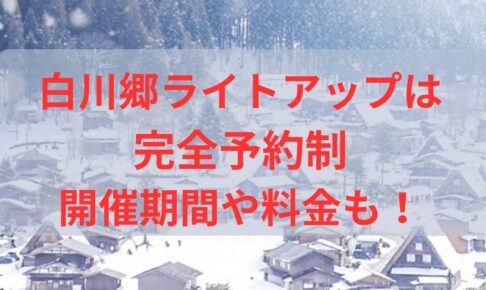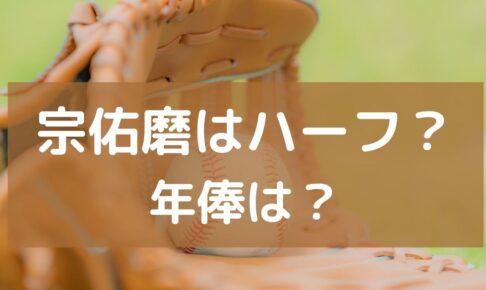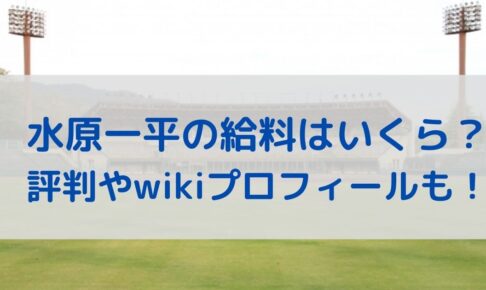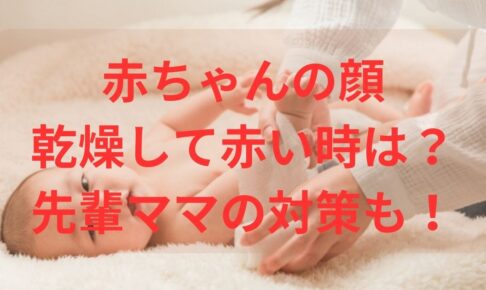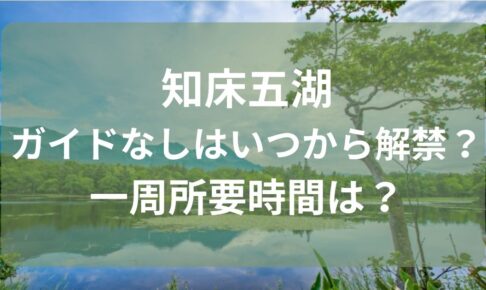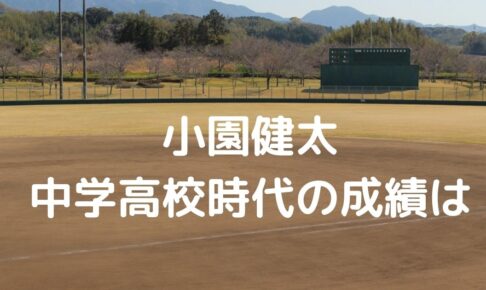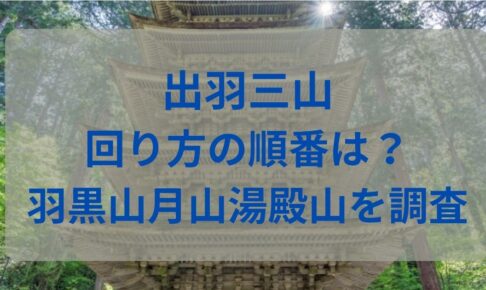富士山が世界文化遺産に登録されてから注目を浴び、富士山登山に興味のある人が増えてきました!
富士山登山や、海外での高所の観光などで心配しなければならないことのひとつが高山病ですね。
富士山登山の際、初心者が気になる高山病対策と予防について「富士山登山の高山病対策と予防は?かかりやすい人の症状は?」と題し、経験をふまえてお伝えします。
スポンサーリンク
富士山登山の高山病とは?

1800m~2500mを超えると高山病に注意です!
富士山登山の4ルートの五合目の標高を調べたところ
- 「吉田口ルート」の五合目は、標高2305m
- 「御殿場口ルート」の五合目は、標高1440m
- 「須走口ルート」 の五合目は、標高2000m
- 「富士宮ルート」の五合目は、標高2400m
御殿場口ルート以外は、注意しなければならない標高ですね。
標高が高くなると皆さんもご存じの通り気圧が低くなります。
気圧が低くなると酸欠状態になっていきます。
つまり「血中酸素濃度の低下」です。
この「血中酸素濃度の低下」により発症する頭痛や吐き気などの症状が「高山病」なのです。
スポンサーリンク
富士山登山の高山病症状とは?
吉田ルートではご来光がどこからでも拝めるので、急がずゆっくり登りましょう。
7月12日水曜日。富士山吉田口六合目からの #御来光 の様子です。
— 富士山ガイド.com (@fujisanguide) July 11, 2023
吉田ルート(#吉田口登山道)は、五合目より上では、ほとんどの場所から御来光を望むことができ、山頂付近での混雜回避ができちゃいます。#富士山 #吉田ルート #富士登山 #六合目 #富士吉田 #山梨 #Mtfuji #fujiyoshida pic.twitter.com/Ag3MMG689O
富士山登山でよく発症するのは「軽症型の高山病」で、症状としては 次のようなものです。
頭痛
吐き気
嘔吐
睡眠障害
食欲不振
めまい
耳鳴り
倦怠感
重症化すると「高地脳浮腫」や「高地肺水腫」といった「重度の高山病」を引き起こし非常に稀に危険な状態になることがあります。
あまり症状がひどいと思う時は、高山病を甘く考えず診療所等で診てもらいましょう。
スポンサーリンク
富士山登山の高山病対策は?
明日(7/22)も天気予報では、天気に恵まれそうですね!
— 富士宮口ガイド組合 (@mt223guide) July 21, 2021
雲がなければ、本当に直射日光が強い日々が続いてます。
高山病&熱中症対策として、しっかり水分補給をして富士登山するようにしましょう!#富士山2021 #富士山 #mtfuji#富士登山 #富士宮口 #富士宮ルート pic.twitter.com/TX6TJ2XONN
1.体調管理
まずは、体調を万全の状態で登山に臨むということが大事です。
登山前日は深酒をせず睡眠をしっかり取って体調管理に気をつけ、万全の状態で登山に臨みましょう。
2.身体を慣らす
富士山登山といえば、五合目から登るという人が多いですよね?
五合目のスタート地点で、 「いざ頂上めざし出発だ!」 と気持ちがはやるのではないですか?
ここは、はやる気持ちを抑えて五合目で1時間から2時間、薄くなってきた酸素に身体を慣らしてから登り始めましょう。
身体を慣らすことで高山病のリスクも低くなります。
3.ゆっくり登る
速く登りたい気持ちは山々ですが、高山病のリスクを下げるためには、ゆっくりしたペースで登ることをおすすめします。
ゆっくり登ることが、高山病予防の最善策といわれています。
グループで登る場合は、体力の低い人に合わせることが大切!
休息もこまめに取るようにしましょう。
4.呼吸
腹式呼吸を心がけます。イメージとしてはローソクを吹き消すという感じで吐き出し、意識して大量の空気を吸い込むようにしましょう。
呼吸が浅くならないことが大切です。
5.水分
水分を摂ることはとても大事です。
とにかく喉が渇いていなくても、こまめに水を飲んでください。
富士山では水は貴重で高価です。大量にリュックで持っていくには重いのでついついセーブしがちですが2リットルくらいは必要です。
1リットル持参して残りは山小屋で購入しても良いですが標高が高くなると1本500円と高くなります。
水を飲むことで効率よく酸素が運ばれ、さらに熱中症対策にもなります!
6.身体を締め付けない
ズボンのベルト、リュックの腹部のベルトを締め付けないようにしましょう。
スナック菓子の袋が標高の高い山でパンパンに膨れているのを見たことはありませんか?
これと同じように身体も膨張するので、ベルト等を締め付けると徐々にきつくなり気分が悪くなる人もいます。
ピッタリした服やジーンズは着ないようにしましょう。
その他
過激な運動は、やめましょう。
アルコールの摂取・睡眠薬の内服には注意が必要です。
鉄分不足から貧血を起こす人は「鉄分」の摂取をしましょう。
スポンサーリンク
富士山登山で高山病症状が出たら?
高山病の症状が出たらそれ以上登らない、つまり高度を上げない事が大切です。
症状が完全になくなってから登りましょう。
もし改善がみられない場合は、苦渋の選択になるかもしれませんがあきらめて下山を選択しましょう。 あきらめる勇気!
おかしくなったら、低い地点まで下りるのが鉄則です。

高山病にかかりやすい人は?
高山病にかかりやすい人かどうかは、実際に登ってみないとわからないそうです。
高山病にかかりやすい人かどうかを調べる方法もないそう。
高山病になりやすいかどうかは、それぞれの個人による差が大きく、なりやすいかどうかを調べる方法もありません。また、今までの経験によれば、高山病のかかりやすさは生まれつきのもので、次第になれることもなく、トレーニングによって改善されることもありません。
引用元:日本旅行医学会トピックスー高山病のかかりやすさは生まれつき
スポンサーリンク
まとめ
楽しく富士山登山を終えるためには、ケガなく、病気なく、事故なくが大切です。
どれも、細心の注意をすることで避けられることが多いですよね。
高山病対策をまとめると、登山前日の体調管理、当日は5合目で身体を慣らす、登山中のこまめな水分補給、呼吸を意識しながら焦らずゆっくり登るというのが予防のポイントです。
天気が良く、富士山からご来光が見られたら最高の思い出になるでしょう。 高山病対策をして楽しい富士登山の思い出をつくってください。
スポンサーリンク